射出成形において、製品設計や金型設計の中で避けて通れない概念の一つが「アンダーカット」です。アンダーカットは、製品の形状により、金型の通常の開閉方向(基本的には上下方向)だけでは製品を金型から取り出すことができない箇所を指します。例えば、側面に開いた穴や横向きの突起、逆テーパー形状などが該当します。
製品にアンダーカットがある場合、金型構造を工夫して、成形後に無理なく製品を離型(取り出す)できるようにする必要があります。アンダーカットを適切に処理しないと、製品が金型に引っかかって破損したり、金型自体にダメージを与えるリスクがあります。
アンダーカット部が発生する例
- 側面に開いた穴(貫通孔)
- 横向きのリブやフック状の突起
- ネジ山などの回転形状
- 組立用の爪(スナップフィット)などの逆方向の形状
これらは、製品機能上必要不可欠な場合が多く、設計上アンダーカットを避けられないことも多々あります。そのため、金型設計の工夫により、これらのアンダーカットを適切に処理する必要があります。
アンダーカット部の処理方法
アンダーカットを処理するためには、製品形状と金型構造を考慮し、いくつかの方法を選択します。主な処理方法は以下のとおりです。
スライドコア
スライドコアは、金型の側面からスライドする部品で、横方向のアンダーカットを形成し、型開き時にその部分を引き抜く構造です。成形時には金型と一体化してアンダーカット部を作り、成形終了後は横にスライドして製品を離型可能にします。
スライドコアはアンダーカット処理で最も一般的かつ信頼性の高い方法であり、多くの金型で採用されています。ただし、構造が複雑になるため、金型の製作コストが上がる傾向があります。
リフター
リフターは、成形品を金型から押し出す「押し出しピン(エジェクタピン)」の一種で、斜め方向に動かすことによって、アンダーカット部を回避しながら製品を取り出す仕組みです。
リフターは、製品のアンダーカット位置が型開き方向にある程度近い場合に適しています。ただし、リフターは摩耗しやすく、長期間の使用で精度が低下するリスクがあるため、定期的なメンテナンスが必要です。
油圧・空圧コア(可動コア)
大型製品や、自動機での成形ラインなどでは、油圧や空気圧を用いて動かす可動コアを使用する場合があります。この方式では、複雑なアンダーカット形状にも対応可能で、金型の一部を外部制御で動かして離型処理を行います。
ただし、これらのシステムは設計と管理が複雑になり、導入コストも高くなります。製品の量産性や成形条件に応じて、使用の是非を検討する必要があります。
インサート成形/後加工
どうしても離型が困難なアンダーカットは、別部品を成形後に組み付ける「インサート成形」や、「後加工(組立や穴あけ加工)」として処理する方法もあります。
この方法は、金型の構造を簡素に保ちつつ、製品設計の自由度を高められるメリットがありますが、組立工程が増える分だけ工数やコストも上がるため、製品の用途や数量に応じて選択します。
設計時のポイントと注意点
アンダーカットは、金型設計において最もコストと構造に影響を与える要素の一つです。そのため、製品設計段階で以下のような点に注意することが求められます。
- アンダーカットを極力避ける形状を優先する。
- 必要なアンダーカットは、離型処理がしやすい位置に設ける。
- スライドコアやリフターの使用を前提とした構造にする。
- 金型の保守性や寿命を考慮し、可動部の負荷を減らす工夫をする。
また、アンダーカット処理は設計者だけでなく、金型製作担当者との連携が重要です。実際の金型加工や成形条件を踏まえたうえで、最適な構造を構築することが高品質な製品づくりにつながります。
まとめ
射出成形金型におけるアンダーカットは、製品の機能性と形状に深く関係する要素です。アンダーカットがあることで金型構造が複雑化し、コストや保守性にも影響を与えますが、スライドコア、リフター、可動コア、インサートなどの手法を用いれば、適切に対処可能です。
製品設計の初期段階から金型構造を意識し、アンダーカットの処理方法を事前に検討することで、無駄なコストやトラブルを防ぎ、スムーズな量産につながります。
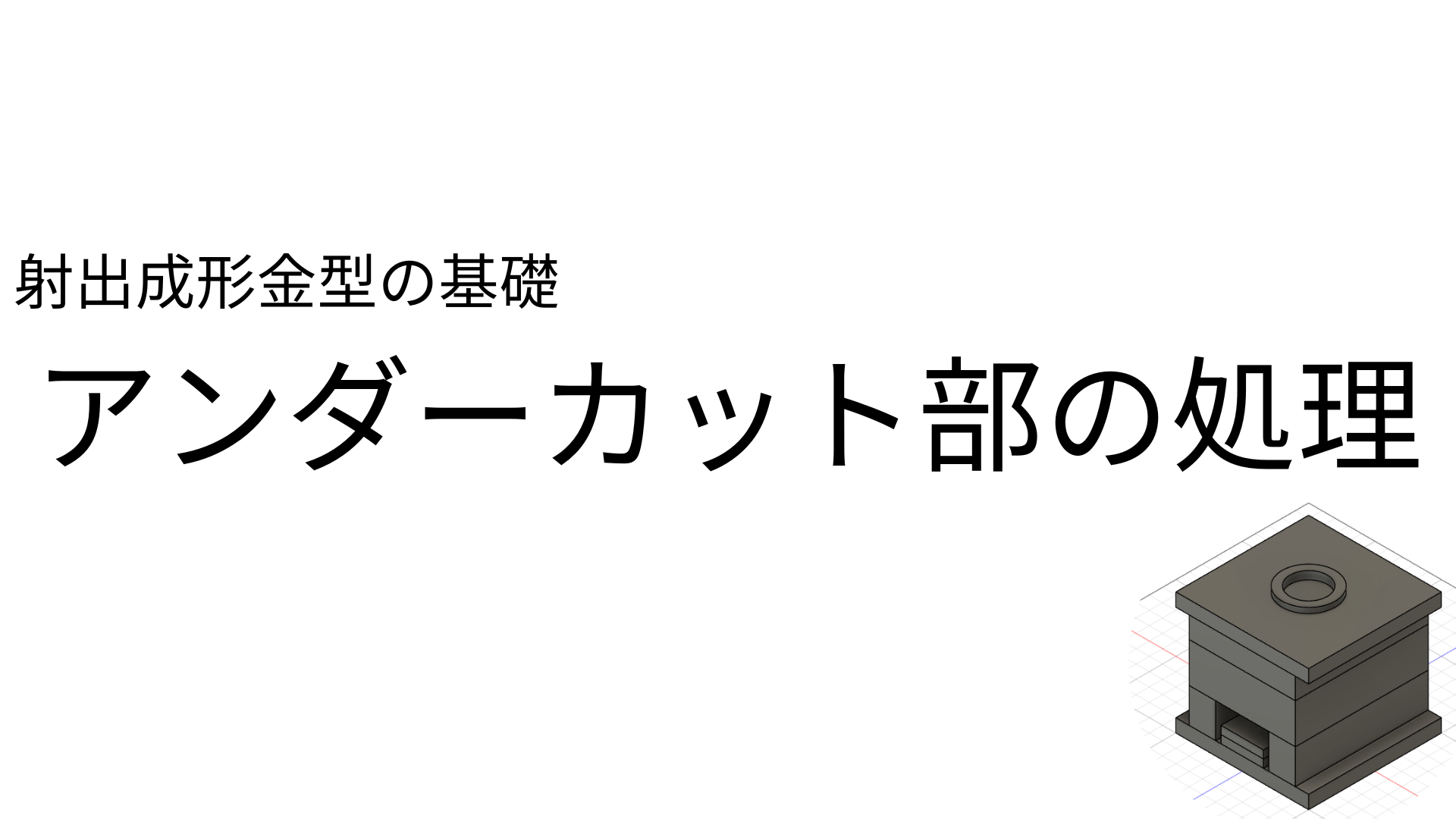
コメント