射出成形における収縮率とは?
射出成形で避けて通れないのが「収縮」です。収縮率とは、成形品の寸法が金型寸法に対してどれだけ縮むかを示す値です。一般的には「線収縮率」として扱われ、(金型寸法-成形品寸法)/金型寸法で計算します。一方、材料メーカーのデータシートで示されるのは「体積収縮率」に近く、線収縮率とは区別する必要があります。
なぜ収縮が起きるのか-物理的メカニズム
樹脂は加熱すると分子が自由に動き、冷却で密に固まります。この際に体積が縮むため、収縮が発生します。特に結晶性樹脂(PP、PE、PAなど)は結晶化度が高まるほど大きく収縮し、非結晶性樹脂(ABS、PC、PMMA)は比較的収縮が小さいのが特徴です。さらに成形条件も影響し、例えば金型温度が高いと結晶性が進んで収縮率が大きくなることがあります。
収縮率の代表的な数値(樹脂別一覧)
一般的な収縮率の目安は以下の通りです。
| 樹脂 | 収縮率(%) |
| PP | 1.5~2.5 |
| PE | 1.5~3.5 |
| ABS | 0.4~0.7 |
| PC | 0.5~0.7 |
| PA | 0.7~1.2 |
| POM | 2.0~2.5 |
ただし、これらはあくまで目安であり、実際の成形条件(ゲート位置、厚み、保圧時間など)によって変動します。材料データシートをそのまま金型設計に使うと誤差が出る場合があるので注意が必要です。
収縮率と設計-金型設計での考え方
金型設計では、収縮率を考慮してキャビティ寸法を大きめに設計します。たとえば収縮率1%の樹脂で最終製品を100 mmに仕上げたい場合、キャビティ寸法は101 mm程度にするのが基本です。
また、肉厚が大きい部分は収縮も大きいため「ヒケ」が発生しやすく、薄肉部分との差で「反り」が発生します。さらに繊維強化樹脂では**流動方向と直交方向で収縮率が異なる(異方性)**ため、設計段階での配慮が重要です。
収縮不良の種類と対策
収縮率が適切にコントロールできないと、以下のような不良が生じます。
- ヒケ:厚肉部の収縮が大きいため、表面がへこむ現象
- 反り:収縮が不均一で部品全体が変形する
- 寸法不良:収縮率の見積もり誤差で寸法精度が出ない
対策としては
- 保圧時間を長くして樹脂を十分に充填する
- 金型温度やバレル温度を調整して結晶化をコントロールする
- CAE解析を用いて事前に収縮挙動を予測する
などが有効です。
現場で役立つ収縮率のチェックリスト
実務では「カタログ値」と「実測値」が食い違うケースが多くあります。そのため、以下のような視点で収縮を管理すると精度が高まります。
- 材料ロットが変わったら収縮率も確認
- 再生材を混ぜると収縮率が変動する
- 成形条件がわずかに変わっても収縮に影響する
現場で収縮を“数値”として把握し、経験値と組み合わせることで不良削減に直結します。
まとめ:収縮率を理解すれば不良低減と精度向上につながる
射出成形における収縮は避けられません。しかし、樹脂の種類や条件による違いを理解し、設計・成形・検証の各段階で適切に反映すれば、不良の大幅削減と製品精度の向上が可能です。
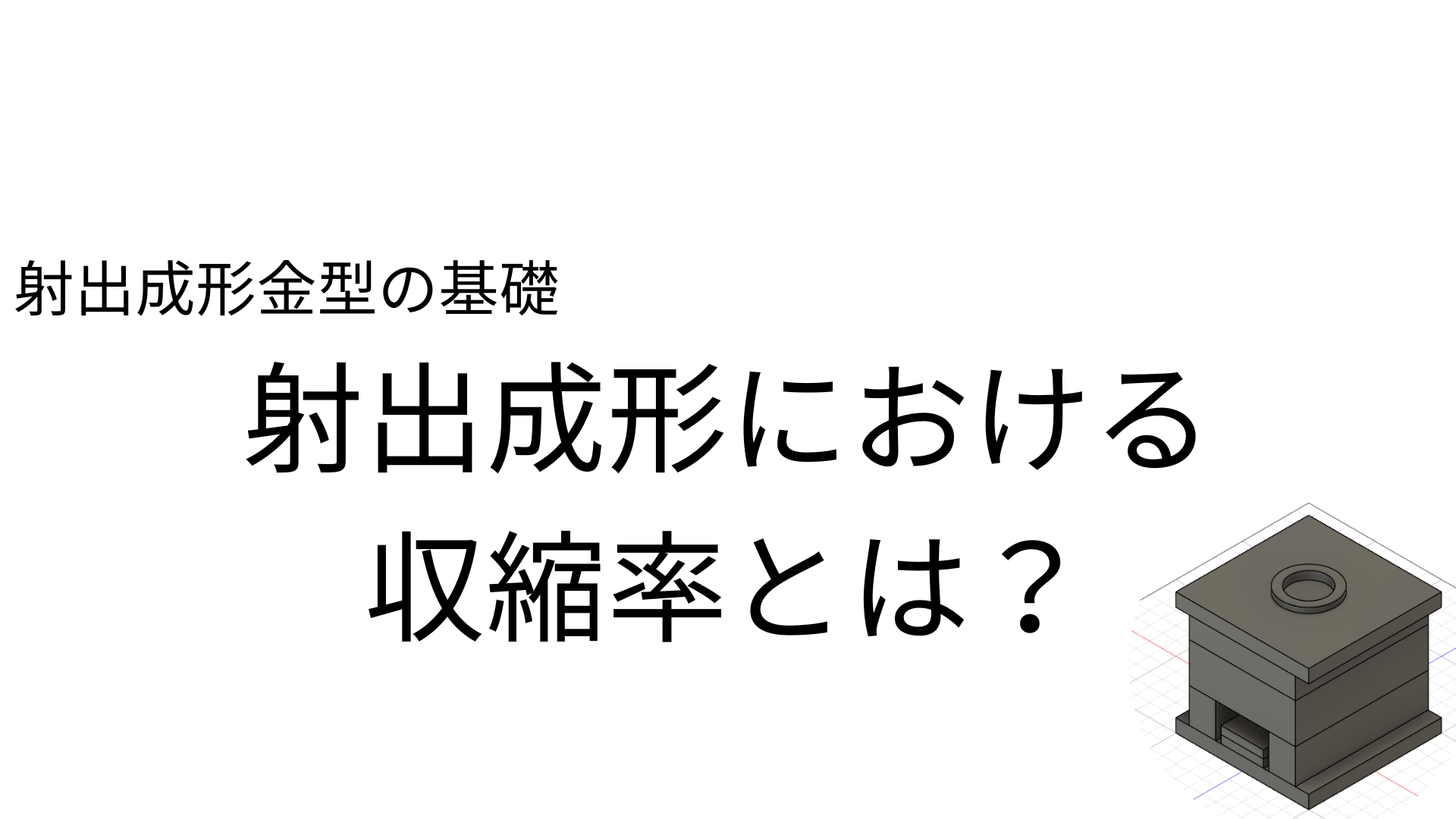
コメント